【統計】ロジスティック回帰分析
ロジスティック回帰分析について。
【目次】
今回はモデル作成まで。モデルの評価は別記事で。
計算式等
ロジスティック回帰は二値分類()で用いられる分析手法。
モデル式は回帰分析と似ているが、シグモイド関数を使って0~1の範囲の結果を出すことが特徴(通常の回帰分析では0~1の範囲を超えてしまい、解釈不能な結果になってしまう)。
(青線:ロジスティック回帰、緑線:単回帰分析)

モデル式、シグモイド関数および損失関数はそれぞれ次のとおり。
モデル式
シグモイド関数(活性化関数)
交差エントロピー誤差(分類問題の損失関数)
※ ln( ) は自然対数。 は実測値で
です(正解ラベルとも言われます)。
交差エントロピー誤差は、対数尤度にマイナスをつけて0を最小値としたもの(負の対数尤度)。式の第一項( )で実際にイベントが起きたデータ(
)に対する予測誤差を計算する(予測90%なら10%が誤差)。式の第二項(
)でイベントが起きなかったデータ(
)に対する予測誤差を計算する(予測10%なら10%が誤差)。
第一項も第二項も の時に
となることから、実測値と予測値が完全一致すれば合計0で誤差なしとなる。
※イメージ的には紫の棒が の時の
、オレンジの棒が
の時の
。
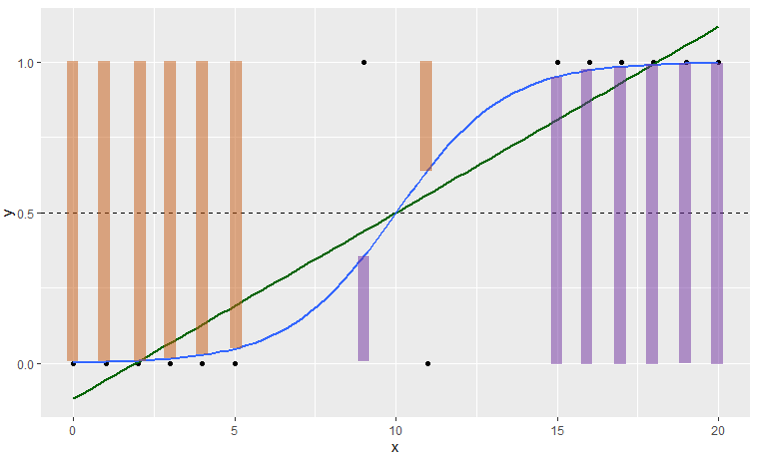
対数尤度関数の計算方法についても掲載。
対数尤度関数
尤度関数
※尤度関数は0~1の確率を "かけ算" するため、値がかなり小さくなってしまう(コンピュータ計算に不向き)。そのため、対数変換して確率の "足し算" とした対数尤度関数が広く使われる。
そして、肝心の回帰係数 β の計算方法は次のとおり。
回帰係数 β の計算方法
式中に があるため、"回帰係数 β を算出するために回帰係数 β が必要" ということになる。本記事ではニュートン・ラフソン法(以降、ニュートン法)による回帰係数の更新方法を取り上げる。
ニュートン法では既存の回帰係数 と演算後の回帰係数
との差がなくなるまで更新を繰り返す。最適解の算出には交差エントロピー誤差のヘッセ行列(H)と重み付き行列(R)を用いる。このRはシグモイド関数の微分の対角行列。
これらをまとめると次の図解。
近似的な方法
簡易的にロジスティック回帰分析を行う方法として、ロジット変換した値を目的変数にした回帰分析がある。二値を Yes / No の数で表すとロジット変換は次の式。
なお、0の対数変換 は計算できないため、0.5 を加算してロジット変換する方法がある。これを経験ロジットと言う。
また、この回帰分析に重みを加えたい場合、ロジットの分散の逆数を重みとする(重み付き回帰分析)。経験ロジットを使う場合は3つ目の式。
最後に、覚えておくと良さそうなシグモイド関数の性質をメモ。
シグモイド関数の性質 ←オッズ比
ノート
今回も簡単なデータで計算手順を見てみる。
■ サンプルデータ
| X1 | X2 | Nyes | Nall | Pyes | Logit | 経験Logit |
| 5 | 0 | 1 | 20 | 0.050 | -2.944 | -2.565 |
| 5 | 1 | 6 | 22 | 0.273 | -0.981 | -0.932 |
| 10 | 0 | 9 | 25 | 0.360 | -0.575 | -0.552 |
| 10 | 1 | 16 | 30 | 0.533 | 0.134 | 0.129 |
| 15 | 0 | 19 | 30 | 0.633 | 0.547 | 0.528 |
| 15 | 1 | 28 | 30 | 0.933 | 2.639 | 2.434 |
今回は近似的な方法で算出した回帰係数 β を初期値にする
その後、ニュートン法を用いて回帰係数 β を更新し、最適解を探す。
初期値設定

LINEST関数で計算。目的変数は経験ロジット。今回は重み付き回帰分析はしていない(単に初期値を得るためなので)。
回帰係数 β はそれぞれ 。
※LINEST関数の使い方は単回帰分析で記載。
回帰係数 β の更新1回目

初期値の回帰係数 β をもとに予測値 を算出する。
サンプルデータの1行目は なので次のとおり。※上図Excel A列の
は切片項用に 1 を設定。
次にヘッセ行列を求める。
<式の再掲>
サンプルデータの1行目を取り上げると R は 。
ヘッセ行列は次のとおりで、今回は切片+説明変数2つの3次元なので3×3の行列になる。
※ 今回の集計表はレコードをまとめているため、計算式に「 」を入れている。
さらに を求める。
※ 今回の集計表はレコードをまとめているため、計算式に「 」と「
」を入れている。「
」は
の時だけ0以外の値を持つため「
」としている。
これら計算結果から回帰係数 β を更新すると次のようになる。
それぞれの更新前後の差は 0.00306, 0.00198, 0.08494 で差があるので更新を続ける。
回帰係数 β の更新2回目

更新2回目は で更新前後の差は 0.00508, -0.00043, -0.00206 。だいぶ良くなったが、まだ差があるので更新する。
回帰係数 β の更新3回目
 更新3回目は
更新3回目は で更新前後の差は 0.000000, 0.000000, 0.000000 。更新前後の回帰係数 β が同値で差がなくなった。
よって更新はここまでにして次を最終モデルとする。
Rでの実行:
> ads <- data.frame(
+ x1=c(rep(5,20),rep(5,22),rep(10,25),rep(10,30),rep(15,30),rep(15,30))
+ ,x2=c(rep(0,20),rep(1,22),rep(0,25),rep(1,30),rep(0,30),rep(1,30))
+ ,y=c(rep(0,19),rep(1,1),rep(0,16),rep(1,6),rep(0,16),rep(1,9),rep(0,14),rep(1,16),rep(0,11),rep(1,19),rep(0,2),rep(1,28))
+ )
> fit1 <- glm(y ~ x1 + x2, family=binomial, data=ads)
> summary(fit1)
Call:
glm(formula = y ~ x1 + x2, family = binomial, data = ads)
Deviance Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-2.0812 -0.8307 0.4935 0.8906 2.2684
Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -4.10022 0.72055 -5.690 1.27e-08 ***
x1 0.32135 0.05562 5.778 7.58e-09 ***
x2 1.32386 0.40344 3.281 0.00103 **
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance: 217.64 on 156 degrees of freedom
Residual deviance: 164.56 on 154 degrees of freedom
AIC: 170.56
Number of Fisher Scoring iterations: 4
SASでの実行:
data ads(drop=i); do i=1 to 1; x1= 5; x2=0; y=1; output; end; do i=1 to 19; x1= 5; x2=0; y=0; output; end; do i=1 to 6; x1= 5; x2=1; y=1; output; end; do i=1 to 16; x1= 5; x2=1; y=0; output; end; do i=1 to 9; x1=10; x2=0; y=1; output; end; do i=1 to 16; x1=10; x2=0; y=0; output; end; do i=1 to 16; x1=10; x2=1; y=1; output; end; do i=1 to 14; x1=10; x2=1; y=0; output; end; do i=1 to 19; x1=15; x2=0; y=1; output; end; do i=1 to 11; x1=15; x2=0; y=0; output; end; do i=1 to 28; x1=15; x2=1; y=1; output; end; do i=1 to 2; x1=15; x2=1; y=0; output; end; run; ods output LackFitChiSq=HOSLEM1; proc logistic data=ads descending; model y(event='1') = x1 x2 / outroc=ROC1 lackfit; output out=OutDS; run;

統計ソフトってすごく便利。。と体感した。
プログラムコード
■ Rのコード
fit <- glm(y ~ x1 + x2, family=binomial, data=ads) summary(fit)
■ SASのコード
proc logistic data=[InputDS] descending; model y(event='1') = x1 x2; output out = [OutDS]; run; quit;
■ Pythonのコード
整備中
交差エントロピー誤差の偏微分
回帰係数 β の計算方法で示した交差エントロピー誤差の偏微分の詳細。
「連鎖律」という方法で微分する。
図解するとこんな感じ。シグモイド関数の微分は公式で z(1-z) になる。

-----
なお、SASやRのロジスティック回帰では「ニュートン法」ではなく、「フィッシャースコアリング法」が用いられているようだった(記事を書き終わってから気づいた)。
この方法は、ニュートン法で使った「ヘッセ行列」を「フィッシャー情報行列」に置き換えたもの。計算コストが良い様子。
今回は更新の仕組みが分かれば良いと思っていたため、この記事は終了。
フィッシャースコアリング法について Wikipedia を参照。
参考
多変量解析実務講座テキスト, 実務教育研究所
【統計】重回帰分析
重回帰分析について。
【目次】
単回帰分析については次の記事。
計算式等
重回帰分析は、多変量 { } の関係を直線で求める分析方法。
モデルは次のとおり。
■ 重回帰モデル
■ 重回帰式
は切片(intercept)、
は回帰係数(regression coefficient)であり、回帰係数は x が1増えた時に y がどのくらい増えるかを表す。
回帰係数の式は、「回帰係数」=「説明変数間の分散共分散行列の逆行列」×「説明変数と目的変数の共分散行列」。
なお、正規方程式から次のように回帰係数を求めることもできる。
※X:説明変数の行列、Y:目的変数の行列、β:回帰係数の行列、t:転置
また、説明変数で表現できないものを残差 と言い、この残差は互いに独立に正規分布
に従う。
重回帰分析は分散分析表で表現することができる。
この分散分析表は単回帰分析で示したものと同じ。
■ 分散分析表
| 変動因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F比 |
|---|---|---|---|---|
| 回帰R | ||||
| 残差e | ||||
| 全体T |
k=説明変数の数
なお、平方和と自由度は の関係が成り立つ。
モデルの評価指標としては次のようなものがある(一例)。
寄与率もしくは決定係数(R-square)
0~1の値を取り、1に近いほど良い。
自由度調整済寄与率もしくは自由度調整済決定係数(adjusted R-square)
0~1の値を取り、1に近いほど良い。
RMSE(Root Mean Square Error, 二乗平均平方根誤差)
相対的な指標であり、値が小さいほど良い。予測値と実測値の誤差に関する指標。
AIC(Akaike's Information Criterion, 赤池情報量規準)
※ MLL : 最大対数尤度(Maximum Log Likelihood), k : 説明変数の数
相対的な指標であり、値が小さいほど良い。2×(k) が説明変数の数に対する罰則項である。
VIF(Variance Inflation Factor, 分散拡大係数)
※ r : 相関係数
多重共線性の評価に用いる。目安として10以上で多重共線性があると考える。
ノート
今回も架空データで簡単に計算方法を見てみる。
x1 = {1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3}
x2 = {2, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 6, 6, 4, 5}
x3 = {5, 6, 5, 2, 3, 5, 7, 5, 4, 6, 5, 9, 6, 5, 5}
x4 = {2, 1.5, 2, 2, 1.5, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4}
y = {1.1, 2.4, 3.3, 2.5, 1.3, 3.1, 2.7, 4.9, 2.4, 3.5, 5.8, 4.4, 3.1, 4.9, 5.3}
Excelでの計算:

モデルの作成
分散共分散行列と逆行列は次のとおり。

よって、今回の重回帰式は次のとおり。
モデルの評価
今回の結果についてVIFを調べてみると x1=38.2, x2=4.3, x3=1.5, x4=40.2 であり、x1 と x4 に多重共線性が疑われる(VIF≧10を目安)。x1 と x4 は相関係数=0.987 であり、かなり強い相関関係がある様子。
したがって、x1 と x4 の一方を外したモデルを作って再評価してみる。また、x3 が非有意(p>0.05)だったため、x3 を外したモデルも作ってみる。
(※この記事では変数選択の手法には触れない。)
<評価モデル>
res1 : y = x1 + x2 + x3 + x4
res2 : y = x1 + x2 + x3
res3 : y = x2 + x3 + x4
res4 : y = x1 + x2
res5 : y = x2 + x4
実行結果は次のとおり。
| res1 | res2 | res3 | res4 | res5 | |
| VIF≧10 | あり | なし | なし | なし | なし |
| R2 | 0.853 | 0.812 | 0.849 | 0.808 | 0.839 |
| adj R2 | 0.794 | 0.761 | 0.808 | 0.776 | 0.812 |
| RMSE | 0.643 | 0.692 | 0.620 | 0.670 | 0.613 |
| AIC | 35.256 | 36.873 | 33.573 | 35.192 | 32.558 |
x1 と x4 の一方を外すことで VIF≧10 の変数は無くなり、多重共線性の問題が解消されたと考えられる。
また、自由度調整済寄与率 の最大値、RMSEとAICの最小値は何れも res5 であり、今回は res5: y=x2 + x4 が最良モデルと考えられる。
なお、res5のモデルは統計的に有意であり(p<0.001)、各回帰係数も有意(x2: p<0.05, x4: p<0.001)。
※今回のモデル比較では、説明変数の数が異なるため、寄与率は は使わず、自由度調整済寄与率
を評価指標としている。
Rでの実行
> ads <- data.frame(x1 = c(1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3)
+ ,x2 = c(2, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 6, 6, 4, 5)
+ ,x3 = c(5, 6, 5, 2, 3, 5, 7, 5, 4, 6, 5, 9, 6, 5, 5)
+ ,x4 = c(2, 1.5, 2, 2, 1.5, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4)
+ ,y = c(1.1, 2.4, 3.3, 2.5, 1.3, 3.1, 2.7, 4.9, 2.4, 3.5, 5.8, 4.4, 3.1, 4.9, 5.3))
> res1 <- lm(y ~ x1 + x2 + x3 + x4, data=ads)
> summary(res1)
Call:
lm(formula = y ~ x1 + x2 + x3 + x4, data = ads)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.8829 -0.3648 -0.2275 0.4359 0.9455
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -1.16286 1.11986 -1.038 0.32354
x1 0.58168 1.25690 0.463 0.65342
x2 -0.87065 0.21243 -4.099 0.00215 **
x3 0.09705 0.12824 0.757 0.46665
x4 1.91008 1.15667 1.651 0.12968
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.6434 on 10 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8525, Adjusted R-squared: 0.7935
F-statistic: 14.45 on 4 and 10 DF, p-value: 0.0003674
> AIC(res1)
[1] 35.25556
> vif(res1)
x1 x2 x3 x4
38.165148 4.331555 1.446171 40.185695
#他のモデル
# res2 <- lm(y ~ x1 + x2 + x3, data=ads)
# res3 <- lm(y ~ x2 + x3 + x4, data=ads)
# res4 <- lm(y ~ x1 + x2, data=ads)
# res5 <- lm(y ~ x2 + x4, data=ads)
SASでの実行
data ads;
input x1 x2 x3 x4 y @@;
cards;
1 2 5 2 1.1 1 1 6 1.5 2.4 1 1 5 2 3.3 1 2 2 2 2.5 1 1 3 1.5 1.3
2 3 5 3 3.1 2 4 7 3 2.7 2 2 5 3 4.9 2 4 4 3 2.4 2 3 6 3 3.5
3 3 5 4 5.8 3 6 9 4 4.4 3 6 6 4 3.1 3 4 5 4 4.9 3 5 5 4 5.3
;run;
proc reg data=ads;
model y = x1 x2 x3 x4 / SELECTION=ADJR RSQUARE AIC RMSE VIF;
run;
プログラムコード
■ Rのコード
library(car)
res <- lm(y ~ x1 + x2, data=InputDS)
summary(res)
vif(res) #-- VIFを算出
AIC(res) #-- AICを算出
■ SASのコード
ods listing close;
ods output SubsetSelSummary=OutputSummary; /* 全変数パターンの評価指標値を取得 */
proc reg data=[InputDS];
model y = x1 x2 / selection=ADJR RSQUARE AIC RMSE VIF; /* VIFはmodelの式のみ */
output out=[OutputDS] p=pred r=residuals; /* modelに書いた式での予測値・残差取得 */
run;quit;
ods listing;
■ Pythonのコード
整備中
偏回帰係数の詳細
の求め方についてもう少し突っ込んでみる。
精度の良いモデルとは、残差 が小さいモデルであるため、残差平方和が最小の時の
を用いれば良いと考えられる(最小二乗法)。
したがって、 について偏微分した式を連立方程式にして最良値を求める。
元:
※合成関数の微分により、[n]×[関数^(n-1)]×[関数の中身の偏微分]。傾き最小を求めるので右辺は0。
ここから -2 を除去して変形すると次のようになり、
①を用いて、 を次の関係式で表すことができる。
この⑤を②に代入して、次の関係式を求める。
③④も同じ処理で次の関係式を求める。
これら⑥⑦⑧を行列表現すると次のようになり、
さらに変形して、各回帰係数の導出式を得る。
つまり、「回帰係数」=「説明変数間の分散共分散行列の逆行列」×「説明変数と目的変数の共分散行列」。
よって、⑤⑨から は次となる。
なお、分散共分散行列を相関行列にすると標準偏回帰係数が得られる。
・・・その他、
①②③④を行列表現すると次のようになり、この方程式からも回帰係数を導出できる(この方程式を「正規方程式」と言う)。
<再掲>
<正規方程式・回帰係数の解>
※X:説明変数の行列、Y:目的変数の行列、β:回帰係数の行列、t:転置
Excelで計算する際は、①の切片項=1(下図のA列)を与えて、公式通り計算。

この方法だと、分析共分散行列を作らず、説明変数と目的変数を直接使って回帰係数を導出できる。
参考
【統計】単回帰分析
単回帰分析について。
【目次】
計算式等
単回帰分析は、2変量 {x,y} の関係を直線(一次式)で求める分析方法。
モデル、式は次のとおり。
■ 単回帰モデル
■ 単回帰式
は切片(intercept)、
は回帰係数(regression coefficient)であり、回帰係数は x が1増えた時に y がどのくらい増えるかを表す。
また、説明変数で表現できないものを残差 と言い、この残差は独立に正規分布
に従う。
単回帰分析は次の分散分析表で表現することができる。
この分散分析表は一元配置分散分析で示したものと同じ。
■ 分散分析表
| 変動因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F比 |
|---|---|---|---|---|
| 回帰R | ||||
| 残差e | ||||
| 全体T |
k=説明変数の数(単回帰分析では1)
なお、平方和と自由度は の関係が成り立つ。
モデルの評価指標としては次のようなものがある(一例)。
寄与率もしくは決定係数(R-square)
0~1の値を取り、1に近いほど良い。
自由度調整済寄与率もしくは自由度調整済決定係数(adjusted R-square)
0~1の値を取り、1に近いほど良い。
RMSE(Root Mean Square Error, 二乗平均平方根誤差)
相対的な指標であり、値が小さいほど良い。予測値と実測値の誤差に関する指標。
ノート
今回も架空データで簡単に計算方法を見てみる。
x = {1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3}
y = {1.1, 2.4, 3.3, 2.5, 1.3, 3.1, 2.7, 4.9, 2.4, 3.5, 5.8, 4.4, 3.1, 4.9, 5.3}
Excelでの計算:

モデルの作成
となるため、
は次のようになる。
よって、今回の単回帰式は次のとおり。
グラフにしたもの。

この計算、ExcelのLINEST関数でも実行できるのでメモ(個人の興味)。
貼付したExcelではP4:Q8が該当箇所。
=LINEST(目的変数の範囲, 説明変数の範囲, 切片項有無, 補正項有無)
[引数]
第1、2引数:特に迷わないと思います。単純なデータ指定です。
第3引数:切片を推定したい場合TRUEとします。FALSEにすると切片=0です。
第4引数:FALSEにすると回帰係数と切片のみを返し、TRUEにすると寄与率、F値、平方和等の情報も計算してくれます。
※今回の例では第3、4引数は両方ともTRUEにしました。
LINEST関数は5行×2列(列数は切片+説明変数の数)を範囲指定し、Ctrl + Shift + Enter で実行する。実行後、各セルに次の結果が得られる。
| 出力結果<再掲> | 各セルの詳細 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
出力結果を見てみると は手計算と同じ結果が得られている。
また、F=18.9384(回帰自由度=1、残差自由度=13)なので、p≒0.0007843となる(セルP12=F.DIST.RT(F値のセル, 1, 残差自由度のセル) )。
なお、回帰係数÷標準誤差で t値を求め、p値≒0.0007843 を得ることができる(セルP10:11)。
モデルの評価
LINEST関数の結果で得られる寄与率は0.5930。
「寄与率=回帰平方和÷全体平方和」の式から分かるように、寄与率は本モデルでデータ全体のどのくらいを説明できるかを示す指標(1に近いほど良い)。
今回のモデルでは6割近くを説明できているという解釈になる。
なお、寄与率は「実測値と予測値の相関係数の二乗」に一致する。
※寄与率は説明変数を増やすだけで大きくなってしまうため、その影響を考慮した指標として自由度調整済寄与率がある。
Rでの実行
> ads <- data.frame(x=c(1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3)
+ ,y=c(1.1, 2.4, 3.3, 2.5, 1.3, 3.1, 2.7, 4.9, 2.4, 3.5, 5.8, 4.4, 3.1, 4.9, 5.3))
> res <- lm(y ~ x, data=ads)
> summary(res)
Call:
lm(formula = y ~ x, data = ads)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-1.570 -0.735 0.120 0.520 1.520
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.8000 0.6404 1.249 0.233580
x 1.2900 0.2964 4.352 0.000784 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.9374 on 13 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.593, Adjusted R-squared: 0.5617
F-statistic: 18.94 on 1 and 13 DF, p-value: 0.0007843
> #-- グラフはこちら
> ggplot(ads, aes(x=x, y=y)) + geom_point() + geom_smooth(method="lm", se=F)SASでの実行
data ads;
input x y @@;
cards;
1 1.1 1 2.4 1 3.3 1 2.5 1 1.3 2 3.1 2 2.7 2 4.9 2 2.4 2 3.5 3 5.8 3 4.4 3 3.1 3 4.9 3 5.3
;
run;
proc reg data=ads;
model y = x;
output out=OutputDS p=pred r=resid;
run;

プログラムコード
■ Rのコード
res <- lm(y ~ x, data=InputDS)
summary(res)
■ SASのコード
proc reg data=[InputDS];
model y = x;
output out=[OutputDS] p=pred r=residuals;
run;
■ Pythonのコード
整備中
回帰係数の詳細
の求め方についてもう少し突っ込んでみる。
精度の良いモデルとは、実測値 と予測値
との差(残差
)が小さいものであるため、残差平方和が最小の時の
を用いれば良いと考えられる(最小二乗法)。

よって、 について偏微分した式を連立方程式にして最良値を求める。
上のイメージのように、残差平方和は二乗のため放物線の形をとり、傾き=0が最小値となる。
元:
※合成関数の微分により、[n]×[関数^(n-1)]×[関数の中身の偏微分]。傾き最小を求めるので右辺は0。
ここから -2 を除去すると、具体的な名称として「残差の合計」と「残差×説明変数の合計」が0になる解を求めることが分かる。
この連立方程式を変形すると次のようになり、
①の式を用いて、 を次の関係式で表すことができる。
この③を②に代入すると が次のように求まる。
よって、③と④から は次となる。
参考
【統計】連関係数(ファイ、ピアソン、クラメール)
クロス表の連関係数について記載。
【目次】
計算式等
次のクロス表で考える。
| Outcome | Total | |||
| 0 | 1 | |||
| Factor | 1 | a | b | AB |
| 2 | c | d | CD | |
| Total | AC | BD | N | |
ファイ係数(Phi coefficient)
-1~1の値を取り、絶対値が1に近いほど関連性が大きい。
2×2のクロス表で用いられ、本係数の絶対値はクラメールの連関係数と一致する。
ピアソンの連関係数 (Pearson's contingency coefficient)または一致係数
※ は連続修正なしの値を用いる。
0~1の値を取り、1に近いほど関連性が大きい。
クラメールの連関係数(Cramer's contingency coefficient)またはクラメールのV(Cramer's V)
※min(R, C)はmin(行数, 列数)であり、行数と列数から最小値を取得する。
※ は連続修正なしの値を用いる。
0~1の値を取り、1に近いほど関連性が大きい。
カイ二乗統計量の計算は以下の記事。
計算例
今回は2×2と3×3のクロス表で各係数を見てみる。
2×2のクロス表

ファイ係数:
ピアソンの連関係数:
クラメールの連関係数:
Rでの実行:
> library(vcd)
> mtx1 <- matrix(c(30, 18, 10, 25), nrow=2, byrow=TRUE)
> vcd::assocstats(mtx1)
X^2 df P(> X^2)
Likelihood Ratio 9.5650 1 0.0019832
Pearson 9.3323 1 0.0022515
Phi-Coefficient : 0.335
Contingency Coeff.: 0.318
Cramer's V : 0.335
SASでの実行:
data ads;
input FACTOR OUTCOME CNT @@;
datalines;
1 0 30 1 1 18 2 0 10 2 1 25
;
run;
proc freq data=ads;
table FACTOR * OUTCOME / chisq nocol nopercent;
weight CNT / zeros;
output out=Outds chisq;
run;

3×3のクロス表(2×2以上のクロス表)

ファイ係数:
NA
ピアソンの連関係数:
クラメールの連関係数:
Rでの実行:
> library(vcd)
> mtx2 <- matrix(c(13,6,4,6,8,7,5,13,21), nrow=3, byrow=TRUE)
> vcd::assocstats(mtx2)
X^2 df P(> X^2)
Likelihood Ratio 15.286 4 0.0041429
Pearson 15.244 4 0.0042217
Phi-Coefficient : NA
Contingency Coeff.: 0.394
Cramer's V : 0.303
SASでの実行:
data ads;
input FACTOR OUTCOME CNT @@;
datalines;
1 0 13 1 1 6 1 2 4 2 0 6 2 1 8 2 2 7 3 0 5 3 1 13 3 2 21
;
run;
proc freq data=ads;
table FACTOR * OUTCOME / chisq nocol nopercent;
weight CNT / zeros;
output out=Outds chisq;
run;

(※SASは2×2以上もファイ係数を計算するみたい)
プログラムコード
■ Rのコード
library(vcd)
vcd::assocstats(mtx1)
■ SASのコード
proc freq data=[InputDS];
table VAR1 * VAR2 / chisq nocol nopercent;
weight CNT / zeros;
output out=[OutputDS] chisq;
run;
※カイ二乗検定で一緒に出力してくれる。
■ Pythonのコード
整備中
参考
【統計】相関係数(ピアソン、スピアマン、ケンドール)
相関係数について。
【目次】
計算式等
2変量を x, y とし、x の順位を z、y の順位を w として考える。タイ(同一順位)は平均順位を用いる。
ピアソンの積率相関係数(Pearson product-moment correlation coefficient)
スピアマンの順位相関係数(Spearman's rank correlation coefficient)
ケンドールの順位相関係数(Kendall rank correlation coefficient)
※ただし、i を基準として、i< j の組合せのみ。
散布図を描いて考えると、次を数えている。
A=プロット {} を基準として、右上or左下にあるプロット数の総和。
B=プロット {} を基準として、左上or右下にあるプロット数の総和。
C=プロット {} を基準として、xが同値でない数の総和。
D=プロット {} を基準として、yが同値でない数の総和。
計算例
次の2変量の相関係数を見てみる。簡単のため、データ数は少なくしている。
X={1, 2, 4, 7, 9, 10}, Y={1, 1, 6, 4, 10, 10}
グラフにすると次のとおり。

Excelでの計算は以下。

ピアソンの積率相関係数
Xの平均=5.5, Y の平均=5.335のため次の計算。
スピアマンの順位相関係数
X, Yについて順位を付けたものをZ, Wとする。
Zの平均=3.5, Wの平均=3.5のため次の計算。
ケンドールの順位相関係数
A~Dの計算は、X, Yの順序で整列した {1,1}, {2,1}, {4,6}, {7,4}, {9,10}, {10,10} について、
個々のペアを基準として、自分より後ろのデータとの関係を調べている。
● AとBの計算例:
1番目のペア {1, 1} を基準にすると、次のようにA該当4個(0より大きいもの)、B該当0個(0より小さいもの)。
{1, 1} vs. {2, 1}=(1-2)(1-1)=0
{1, 1} vs. {4, 6}=(1-4)(1-6)=15
{1, 1} vs. {7, 4}=(1-7)(1-4)=18
{1, 1} vs. {9, 10}=(1-9)(1-10)=72
{1, 1} vs. {10, 10}=(1-10)(1-10)=81
また、3番目のペア {4, 6} を基準にすると、A該当2個、B該当1個。
{4, 6} vs. {7, 4}=(4-7)(6-4)=-6
{4, 6} vs. {9, 10}=(4-9)(6-10)=20
{4, 6} vs. {10, 10}=(4-10)(6-10)=24
このような手順で全ペアの該当件数を算出して総和する。
● CとDの計算:
Yの1番目 {1} を基準とすると、次のようにD該当4個(同値でないもの)。
{1} vs. {1}=同値
{1} vs. {6}=同値ではない
{1} vs. {4}=同値ではない
{1} vs. {10}=同値ではない
{1} vs. {10}=同値ではない
また、Yの5番目 {10} を基準とすると、次のようにD該当は0個。
{10} vs. {10}=同値
このような手順で全ての値での該当件数を算出して総和する。
※全ペアの結果は、貼付した Excel Q:AH列 を参照のこと。
Rでの実行:
> ADS1 <- data.frame(X=c(1,2,4,7,9,10), Y=c(1,1,6,4,10,10))
> ADS1$Z <- rank(ADS1$X)
> ADS1$W <- rank(ADS1$Y)
> ggplot(ADS1) + geom_point(aes(X, Y), size=5, color="blue")
> cor(ADS1$X,ADS1$Y,method="pearson")
[1] 0.906666
> cor(ADS1$X,ADS1$Y,method="spearman")
[1] 0.9121593
> cor(ADS1$Z,ADS1$W,method="pearson") #--順位をpearsonで計算しても同じ。
[1] 0.9121593
> cor(ADS1$X,ADS1$Y,method="kendall")
[1] 0.7877264
なお、順位に変換してからピアソンの相関係数を算出すれば、スピアマンの順位相関係数が得られる。
SASでの実行:
data ads;
input x y @@;
cards;
1 1 2 1 4 6 7 4 9 10 10 10
;
run;
proc corr data=ads pearson spearman kendall;
var x y;
run;
プログラムコード
■ Rのコード
cor(ADS$X, ADS$Y, method="pearson") #-- ピアソンの積率相関係数
cor(ADS$X, ADS$Y, method="spearman") #-- スピアマンの順位相関係数
cor(ADS$X, ADS$Y, method="kendall") #-- ケンドールの順位相関係数
■ SASのコード
proc corr data=ads pearson spearman kendall;
var x y;
run;
■ Pythonのコード
整備中
ピアソンの相関係数と順位相関係数
ピアソンの相関係数は、線形の関係性を示す。
一方、スピアマンやケンドールの順位相関係数は順位を扱うため、例えば次の曲線の場合、ピアソンの相関係数=0.98 に対して、スピアマンやケンドールの順位相関係数は1になる。

> ADS2 <- data.frame(X=c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
+ ,Y=c(2,2.1,2.5,3,4,5,6,7.5,7.9,8))
> ggplot(ADS2) + geom_point(aes(X, Y), size=5, color="blue")
> cor(ADS2$X,ADS2$Y,method="pearson")
[1] 0.9807044
> cor(ADS2$X,ADS2$Y,method="spearman")
[1] 1
> cor(ADS2$X,ADS2$Y,method="kendall")
[1] 1
参考
【統計】統計関連記事のサイトマップ
統計関係の記事いくつか書いているので、サイトマップ作りました。
差の評価
| 対応有無 | 目的変数 | 群数 | 検定 | 記事 |
| 対応なし | 連続値 | 2群 | t検定(Student、Welch) | 記事あり |
| 2群以上 | 一元配置分散分析 | 記事あり | ||
| 二元配置分散分析 | 記事あり | |||
| 共分散分析 | 記事あり | |||
| 連続値 or順序変数 |
2群 |
Wilcoxonの順位和検定 |
①記事あり ②記事あり |
|
| 2群以上 | Kruskal-Wallis test | |||
| 対応あり | 連続値 | 2群 | 対応のあるt検定 | 記事あり |
| 2群以上 | 一元配置反復測定分散分析 | 記事あり | ||
| 2群以上 | 二元配置反復測定分散分析 | 記事あり | ||
| 連続値 or順序変数 |
2群 |
Wilcoxonの符号付き順位検定 |
①記事あり ②記事あり |
|
| 2群以上 | フリードマン検定 | 記事あり |
| 対応有無 | 目的変数 | セル | 検定 | 記事 |
| 対応なし | カテゴリ | n×m | Fisher's exact test | 記事あり |
| χ^2検定 | 記事あり | |||
| k×n×m | マンテル・ヘンツェルの検定(CMH検定) | 記事あり | ||
| 対応あり | n×m | マクネマー検定 | 記事あり |
傾向性の評価
| 目的変数 | 検定 | 記事 |
| 連続変数 or順序変数 |
ヨンキー検定(Jonckheere-Terpstra test) | |
| 割合 | コクランアミテージ検定 | 記事あり |
関係性の評価
| 目的変数 | 検定 | 記事 |
| 連続変数 | ピアソンの相関係数 | |
| 連続変数 or順序変数 |
スピアマンの順位相関係数 ケンドールの順位相関係数 |
|
| カテゴリ | ファイ係数 ピアソンの連関係数(一致係数) クラメールの連関係数(クラメールのV) |
多変量解析
| 解析手法 | 記事 |
| 単回帰分析 | 記事あり |
| 重回帰分析 | 記事あり |
| ロジスティックス回帰(理論編) | 記事あり |
| ロジスティックス回帰(モデル評価編:ROC曲線、AUC、ホスマーレメショウ検定等) | 記事あり |
| Lasso回帰(L1正則化)、Ridge回帰(L2正則化) | 記事あり 記事あり |
| 一般化線形モデル(GLM) | 記事あり |
| 一般化線形混合モデル(GLMM) | 記事あり |
| 主成分分析 | 記事あり |
| 因子分析(探索的因子分析・検証的因子分析) | 記事なし |
生存時間解析
| 解析手法 | 記事 |
| Kaplan-meier法 | 記事あり |
| ログランク検定、一般化Wilcoxon検定(Gehan's Wilcoxon)等 | 記事あり |
| コックス比例ハザードモデル | 記事あり |
時系列解析
| 解析手法 | 記事 |
| 自己相関・自己共分散 | 記事あり |
| ARIMAモデル、SARIMAモデル、ARIMAXモデル(理論編) | 記事あり |
| ARIMAモデル、SARIMAモデル、ARIMAXモデル(実装編) | 記事あり |
| 状態・空間モデル | 記事なし |
| 階層ベイズモデル | 記事なし |
あとがき
一先ず、書いてみたいと思った内容をまとめたが。。
すべて書くかは分からない。。。
【統計】クラスカル・ウォリス検定(Kruskal-Wallis test)
クラスカル・ウォリス検定(Kruskal-Wallis test)について。
【目次】
クラスカル・ウォリス検定(KW検定)は3標本以上を評価するノンパラメトリックな手法。
Wilcoxonの順位和検定・マンホイットニーのU検定(以下、Wilcoxonの順位和検定等)は2標本。
帰無仮説、対立仮設
- 帰無仮説
全ての標本の確率分布に差がない(ズレていない)。
- 対立仮設
何れかの標本の確率分布に差がある(ズレている)。
Wilcoxonの順位和検定等と同じく、確率分布の位置のズレを見る。正規分布に依存しないのが特徴。
計算式等
順位和
統計量の算出前に、先ず、比較したい全標本の観測値に全体順位(Rank)をつけて、標本ごとの合計(順位和)を算出する。観測値にタイ(同一順位)がある場合は、順位の平均値をつける。この方法はWilcoxonの順位和検定等と同じ。
H統計量
H統計量は近似的に 分布(
)に従うため、
分布を使って検定を行う。
また、タイ(同一順位)の補正を行う場合、上で求めたH統計量にタイの補正値(D)を除算する。
Wilcoxonの順位和検定等と同じくタイ(同一順位)の補正式第2項の t が同一値の個数を示す。
例えば、{10,10,11,12,12,12} のデータがあるとき、10が2つ、11が1つ、12が3つになるため、それぞれ となり、
の計算で
になる。タイがない数値は解が0になり、タイにだけ働く。
なお、タイがまったくない場合は第2項の解全体が0になり、D=1-0=1になる。 で等価。
計算例
今回は、架空の4標本に違いがあるか評価する。
A {10,10,11,12,12,12}
B {12,13,14,17,19}
C {12,14,15,19,20}
D {16,17,18,20}
Excelでの計算:

Excelの簡単な説明。
・A列:標本のグループ名。
・B列:観測値。小さい順にならべている。
・C列:同値の数を上から数ている(セルC4:=IF(B3<>B4,1,D3+1))。
・D列:同値の最終行のみ表示している(セルD4:=IF(B4=B5,"",C4))。
・E列:分散の補正項用(セルE4:=IF(D4<>"",D4^3-D4,""))
・G列:標本Aの順位(セルG4:=IF($A4=G$3, RANK.AVG($B4,$B:$B,1), ""))
・H列:標本Bの順位(セルH4:=IF($A4=H$3, RANK.AVG($B4,$B:$B,1), ""))
・I列 :標本Cの順位(セルI4 :=IF($A4=I$3, RANK.AVG($B4,$B:$B,1), ""))
・J列:標本Dの順位(セルJ4:=IF($A4=J$3, RANK.AVG($B4,$B:$B,1), ""))
H統計量:
順位和は だったため、
はそれぞれ
になる(Excel L3:P7)。
全体数はN=20のため、公式通り、H統計量は となる(Excel L9:M15)。
タイの補正:
同一値 t の計算()は 150 になる(Excel D:E, P12)。
(今回は 12 が5つあり、 と大きな値がある。)
公式通り、 となり、このDで除算して
が得られる(Excel P13:P15)。
p値:
計算式等で述べたとおり、H統計量は 分布(
)に従うため、次のようになる。
今回の架空データでは、標本間に差がある(p<0.01)。(タイ補正有無問わず)
Rでの実行:
> ads <- data.frame(
+ AVAL = c(10,10,11,12,12,12,12,12,13,14,14,15,16,17,17,18,19,19,20,20)
+ ,TRT01P = c("A","A","A","A","B","A","A","C","B","B","C","C","D","B","D","D","C","B","C","D"))
> ads$TRT01PF <- factor(ads$TRT01P)
> kruskal_test(AVAL ~ TRT01PF, data=ads, method="exact")
Asymptotic Kruskal-Wallis Test
data: AVAL by TRT01PF (A, B, C, D)
chi-squared = 11.722, df = 3, p-value = 0.0084
> kruskal.test(x=ads$AVAL, g=ads$TRT01PF)
Kruskal-Wallis rank sum test
data: ads$AVAL and ads$TRT01PF
Kruskal-Wallis chi-squared = 11.722, df = 3, p-value = 0.0084 デフォルトで使える kruskal.test、coinパッケージのkruskal_testの2つ関数がありますが、どちらもタイ補正ありの結果を得る。
SASでの実行:
タイ補正ありの結果が得られる。
data ads;
do AVAL=10,10,11,12,12,12; TRT01PN=1; output; end;
do AVAL=12,13,14,17,19; TRT01PN=2; output; end;
do AVAL=12,14,15,19,20; TRT01PN=3; output; end;
do AVAL=16,17,18,20; TRT01PN=4; output; end;
run;
proc sort data=ads: by AVAL TRT01PN; run;
proc npar1way data=ads wilcoxon;
class TRT01PN;
var AVAL;
output out=OutputDS wilcoxon;
run;
プログラムコード
■ Rのコード
#-- coinパッケージ
library(coin)
kruskal_test(AVAL ~ Group, data=ADS, method="exact")
#-- デフォルトのstatsパッケージ
kruskal.test(x=ADS$AVAL, g=ADS$Group)
■ SASのコード
proc npar1way data=[InputDS] wilcoxon;
class Group;
var AVAL;
output out=[OutputDS] wilcoxon; /*_KW_,P_KWを取得。*/
run;
■ Pythonのコード
整備中
2標本でもKW検定
2標本のデータについて、Wilcoxonの順位和検定とKW検定を実行すると、どちらも同じ p値が得られる。
> ads <- data.frame(
+ TRT01P <- c("A","A","A","A","A","A","A","A","B","B","B","A","A","B","B","A","B","B","B","B")
+ ,AVAL <- c(4,9,10,11,12,13,13,15,16,16,17,18,18,19,19,20,22,22,23,25)
+ )
> ads$TRT01PF <- factor(ads$TRT01P)
> wilcox_test(AVAL ~ TRT01PF, data=ads, method="exact")
Asymptotic Wilcoxon-Mann-Whitney Test
data: AVAL by TRT01PF (A, B)
Z = -2.9305, p-value = 0.003384
alternative hypothesis: true mu is not equal to 0
> kruskal_test(AVAL ~ TRT01PF, data=ads)
Asymptotic Kruskal-Wallis Test
data: AVAL by TRT01PF (A, B)
chi-squared = 8.5878, df = 1, p-value = 0.003384 参考
https://www.dataanalytics.org.uk/adjustment-for-tied-ranks-in-the-kruskal-wallis-test/
https://www.lexjansen.com/wuss/2018/26_Final_Paper_PDF.pdf